| 読書ノート / 通史 |
| 物語日本史(下)(講談社学術文庫) | ||
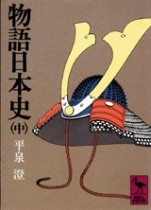 |
編・著者 | 平泉澄/著 |
| 出版社 | 講談社 | |
| 出版年月 | 1979/2/10 | |
| ページ数 | 207 | |
| 判型 | A6版 | |
| 税別定価 | 563円 | |
本書は、同じ著者による「少年日本史」(皇學館大学出版部)を3部に分割した文庫版の中巻です。「少年日本史」はこちらのサイトで読むことができます。文庫版ではやや難しい漢字が平仮名に置き換えられている以外は、内容は同じものです。以下、本書の引用はこちらのサイトを利用させてもらいました。
●主役は国学者で脇役が戦争物
本書の内容は次のようになっています。江戸時代の国学者や勤皇思想家が主役で、戦国の三英傑と幕末の戦争物が脇役となっています。山鹿素行や山崎闇斎など教科書で名前だけ知っている程度なので、勤皇思想の流れを理解する上で参考になります。
|
57 織田信長 58 豊臣秀吉 59 徳川家康 60 徳川家光 61 山鹿素行 62 山崎闇斎(上) 63 山崎闇斎(下) 64 本居宣長 65 水戸光圀 66 井伊直弼 67 橋本景岳 68 吉田松陰 69 孝明天皇 70 明治維新 71 西郷隆盛 72 明治天皇 73 二大戦役 74 大東亜戦争 |
●秀吉を賞賛、家康には辛口
信長については、著者は、次のように(12ページ)評しています。「信長の目的とするところは、朝廷の再興だった」というのは、あまり聞かない話です。
| 天下布武を目標とする信長は、東は三河の徳川家康と和して後顧の心配がないようにし、西に進んで美濃を取り、岐阜城を拠占としました。そして永禄十一年九月、燈心の抵抗を排除して京都に入り、山城、摂津、河内、和泉を平定し、一時流浪していた足利義昭を将軍の座に徹しました。しかも信長の目的とするところは、足利幕府の再興ではなくして、朝廷の再興でありました。そのために兵力をもって御所の御警衛につとめ、費用を献じて宮中の御修理を願い、また皇室御領の復旧を沙汰しましたので、朝廷の御威光再び輝くに至りました。そして永禄十三年には、将軍義昭をして、何事によらず、油断りく朝廷にお仕え申し上げるように約束させ、元亀三年には、義昭が、約束にそむいていっこうに参内せず、朝廷をなおざりにしていることを詰問したのでした。しかるに義昭の態度は改まらず、かえって武田信玄と通じて、信長を討つ計画を立てましたので、天正元年、信長は義昭を京都より追放し、足利幕府はここに全く亡びました。そしてこれより後の信長は、朝廷の重臣として天皇をいただいて、天下の統一に専念したのです。 |
| 次に聚楽の行幸。秀吉は、先年より京の内野に壮麗を極めた大邸宅の建築を始めていましたが、それが天正十五年の九月に完成して、之を聚楽第と名づけました。秀吉は、信長と同じく、最も皇室を尊びましたので、この大邸宅が出来上がりますと、ここに行幸を仰ぎました。翌十六年四月十四日、後陽成天皇行幸、その御出でましの際には、関白秀吉、みずから天皇の御裾を取って、御供申し上げました。公卿も数多く供奉すれば、諸大名も行列に加わり、それぞれ装束に意匠を凝らしたので、見物の人々は非常な感動でした。御滞在、初めは三日間の予定でしたが、天皇は非常な御満足で、之を五日に延長せられました。秀吉は深く之を喜び、宮中へ御料所を献上すると共に、織田信雄、徳川家康、宇喜多秀家、前田利家等数十人の大名に命じて、皇恩を有り難く感佩(かんぱい)する事、皇室御料を永久に守るべき事を、堅く誓約させました。秀吉は、「頼朝以後では自分だ」と云う事を、よく云いましたが、その武力の天下を威圧して点においても、またその天皇を尊び、武士に対して勤王を厳命した点においても、正に頼朝と相並んで双璧と云ってよいでしょう。 |
|
家康は京都を遠く離れ、朝廷とは全然別個に、江戸に幕府を開いたのですから、その点では鎌倉幕府に似ています。つまり家康が目標とし、手本としたのは頼朝であったのです。そう云えばこの両人は、その経歴が非常によく似ていましょう。(中略) 然し真似ると云っても、自分の都合の良いように模倣しただけで、朝廷に対する態度などは、頼朝よりは遥かにきびしいものでした。 |
●朝鮮出兵は「双方の不幸」
秀吉の朝鮮出兵については、著者は、次のように(33〜34ページ)「我が国としては、得るところ極めて少なく、朝鮮にとっては、すこぶる迷惑な、つまり双方の不幸」と評しています。戦争に駆り出された日本の民衆にとって「不幸」なのでしょうか、侵略した権力者が失敗したことが「不幸」なのでしょうか。「唐南蛮までも皇威に服するようにしたいという希望または計画を、はっきりと述べていた」ことや300年も前の元寇について言及していますが、それらが朝鮮出兵を正当化するという意味なのでしょうか。
| これより秀吉の亡くなるまでの八年間、最大の問題は、海外への出兵でありました。これは我が国としては、得るところ極めて少なく、朝鮮にとっては、すこぶる迷惑な、つまり双方の不幸でありました。秀吉という人は、まことに傑出した英雄でありましたが、その英雄たる本質を最もよく発揮したのは、明智及び柴田の征伐であって、後年に及んでは、その生活も乱れ、その判断も軌道をはずれるところがありました。さきには信長が、強敵がなくなって後に油断が出て、ついに身を亡ぼした悲しむべき例を見ましたが、今度は秀吉に驕りが出てきたのです。人はすべて、その全盛の日を慎まねばならないのです。ちょうど秀吉に驕りが出てき、慎みのなくなった時に、海外への出兵の起ったことは、残念でありました。しかし海外へ発展したいとの希望は、秀吉には早くからあり、また秀吉ばかりでなく、ほかの人々にもあったようです。天正五年に秀吉は信長に向って、自分には大陸で領地を与えていただきたいと言ったと伝えられ、天正十年秀吉は亀井蛙矩(これのり)を琉球守、ついで台州守に任じたというのが、それです。そして天正十四、五年からは、唐南蛮までも皇威に服するようにしたいという希望または計画を、はっきりと述べております。けだしかつて蒙古よりたびたび無礼な文書をつきつけられ、やがて前後二回大軍の侵攻を受け、それにはシナ本土の軍兵も、また朝鮮の部隊も、参加し、誘導し、協力したのでしたから、これに対する憤激が強く残り、長く伝わっていたので、それが今時機を得て、表面に現れてきたのでしょう。そして初めは朝鮮はただ通過して、直ちに明国に入るつもりであったのが、朝鮮の抵抗にあって、まずこれと戦い、ついで明の大軍と戦うこととなったのでした。 |
| さても島原の戦い、一揆はたいてい百姓であり、城は応急工作を加えた古い城であり、これを守った人数は三万数千人でありました。それを攻めるに、幕府は鍋島、有馬、立花、細川、松倉などの諸藩に出兵を命じ、総勢十二万余の大軍を動かしながら、鎮圧に五箇月を費し、最初の追討使板倉重昌は討ち死にし、次に現れた松平信綱、知恵伊豆と渾名せられたほどの人でありながら、兵糧攻め以外に手が出ず、ことに重昌戦死の日の戦い、幕府軍の死傷四千、一揆方九十人というのでは、話になりますまい。これを四十年前、朝鮮において明の大軍と戦った際の武功と比べますと、これが同じ日本の武士かと驚くほかはないでしょう。 碧蹄館の戦い(文禄二年)では、京城に迫った明軍二万を、朝からは立花宗茂二千五百の手兵をもって迎え討ち、奮戦して敵を悩ましたる後、午後に至って小早川隆景一万余の兵をひきいて敵軍を潰走せしめたのでありました。蔚山の籠城(慶長二ー三年)は、築城工事中の浅野幸長が突然明の大軍四万数千に囲まれたと聞いて、加藤清正わずか五十人の兵と鉄砲二十挺をもって応援にかけつけ、工事はまだ仕上がらず、兵糧も少なければ、味方の援助の期待できない中を、総勢二千、固く守って屈せず、意外に援軍が到着するや、直ちに明軍を破って潰走させ、城の周辺に残された明兵の死骸をかぞえたところ、一万三百八十六人あったというのでありました。四川の戦い(慶長三年)には、島津義弘、五千未満の兵をもって明兵数万に囲まれ、しかも城門を開いて突撃し、敵の首を取ること、三万八千に上ったというのでありました。その島津義弘は、慶長五年関ヶ原の戦いに西軍に属して戦い、わずかの兵をもってまっすぐに東軍の中を駆け抜け、勝つことはできなかったが、敵にうしろを見せず、そのまま薩摩へ帰り、この戦いに毛利は八十三万石を削られたにかかわらず、島津は元のままに領土を保ち得たのでした。それが四十年前の日本武士でした。何事ぞ、四十年後には、十二万の大軍をもって三万余の一揆と戦い、戦いを交えては味方にばかり死傷が多く、やむを得ず兵糧攻めにして、ようやくのことで解決したのでした。三、四十年平和の日が続き、泰平無事を喜んでいるうちに、心身ともに衰弱したのでしょう。寛永年間すでにかようであれば、それが元禄を経、文化・文政を経て幕末にきますと、旗本八万騎、実際には役に立ちかねること、たいてい想像がつくでしよう。 |
| (2015/9/17) |